
ムカデとは?
ムカデ(百足)は、多足類ムカデ綱に属する陸生の節足動物で、全身に無数の脚を持ち、肉食性で獰猛な捕食者です。日本には40種以上が分布し、特に有名な種類にトビズムカデやアオズムカデなどがいます。多くは湿った落ち葉の下や石の裏、倒木の隙間などに潜み、夜になると活動を開始します。
ムカデはその見た目や動きから恐れられることもありますが、実際には生態系の中で重要な役割を担う生物です。
特徴

- 体長:2cm〜20cm以上(トビズムカデは最大級)
- 体色:黒褐色・赤褐色・青緑色など種によって多様
- 脚の数:体節ごとに1対ずつ、おおむね15対(30本)前後
- 頭部の構造:大きな顎肢(毒腺を含む)を持ち、これで獲物を捕える
- 尾部:最後の一対の脚はやや長く、攻撃・威嚇時に用いることもある
- 感覚器官:触角が非常に発達し、暗所での探索や獲物の察知に利用される
生態と行動

- 食性:完全な肉食性。昆虫、クモ、小型の爬虫類や両生類を捕食
- 活動時間:夜行性。昼間は石の下や落ち葉の中でじっとしている
- 移動能力:非常に俊敏で、獲物を素早く捕らえる能力を持つ
- 繁殖行動:雄は精包(精子の入った袋)を地面に置き、雌がそれを体内に取り入れるという特徴的な間接交尾を行う
- 産卵と育児:一部の種では雌が卵を守り、孵化後もしばらく幼体を保護する
ムカデと人間の関係

- 危険性:大顎(顎肢)による噛傷は強い痛みや腫れを伴うことがある。特に大型種(例:トビズムカデ)には注意が必要
- 毒の作用:局所的な炎症、痛み、まれに発熱やアレルギー反応を引き起こすが、通常は命に関わることはない
- 益虫としての側面:ゴキブリやハエなどの害虫を捕食するため、生態系上では益虫的な立場にある
ムカデの代表種
| 種名 | 特徴 | 分布・備考 |
|---|---|---|
| トビズムカデ | 日本最大のムカデ(最大20cm)。赤い頭と黄色い脚が特徴 | 本州〜南西諸島 |
| アオズムカデ | やや小型で青緑がかった体色 | 全国に分布 |
| イッスンムカデ | 体長2〜4cmで家庭にも侵入しやすい | 全国の住宅周辺にも出現 |
観察のポイント
- 夜の活動:夜間、林道や住宅地で活動中の個体を見かけることがある
- 隠れ家を探す:朽ち木の中や落ち葉の層、石の下などをそっとのぞくと潜んでいることが多い
- 幼体の姿:成体に比べて脚が少なく、色も淡く可愛らしい印象
※観察時は素手で触れないように注意しましょう。特に大型種の咬傷は非常に痛みを伴います。
ムカデと類似生物の違い
| 名称 | 相違点 |
|---|---|
| ヤスデ | 脚は体節ごとに2対。動きは遅く、基本的に草食性。毒はない |
| ゲジゲジ | 脚が非常に長く見えるがムカデと異なり、天井や壁も走れる。咬傷の被害は少ない |
| ゴキブリ | 翅があり、外見や動きが異なる。ムカデは捕食する側 |
基本情報
- 和名:ムカデ
- 学名:Chilopoda(ムカデ綱全体)
- 分類:多足類 ムカデ綱
- 体長:2〜20cm(種により異なる)
- 分布:日本全国
- 活動期:4〜10月(特に梅雨〜夏が活発)
- 生息環境:森林、庭、石の下、落ち葉の堆積層など
タグ(コンマ区切り)
ムカデ,日本昆虫研究所,百足,多足類,節足動物,森林の捕食者,肉食性の虫,咬まれる虫,益虫,夜行性の虫,トビズムカデ,落ち葉の中の虫,自然観察










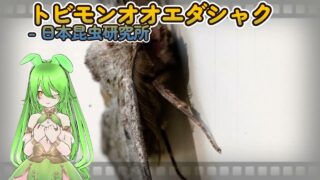










コメント