
##【日本昆虫研究所】エビイロカメムシとは?光沢ある体色と独特な生活史をわかりやすく紹介!
概要

エビイロカメムシは、カメムシ目カメムシ科に属する昆虫で、秋になると特に目立つ存在になります。その名前の通り、エビの殻のような深い赤紫色(海老色)の体色が印象的で、陽光の下では美しい金属光沢を放つこともあります。森林や林縁に生息し、特定の樹木に集まる傾向があるため、昆虫観察の対象としても人気のある種です。
特徴

エビイロカメムシは体長12〜15mm程度で、やや扁平な楕円形の体形をしています。最大の特徴はその独特な体色で、深い赤紫色の上に金属的な輝きがあり、観察環境によっては緑がかった光沢が出ることもあります。
翅の形状は他のカメムシと同様、半翅の構造を持ち、背面には明瞭なX字模様が浮かび上がるのが特徴です。成虫は硬い前翅と柔らかい後翅を使い分けて飛行し、比較的俊敏な動きを見せます。
また、刺激を与えると独特の臭気を放つため、「カメムシ」らしい性質もしっかり備えています。
生態

エビイロカメムシは主にブナ科やカエデ科の樹木に生息し、樹液や未熟な実、若葉から汁を吸う植物食性です。特にコナラ、クヌギ、イロハモミジなどの落葉広葉樹を好みます。
春から夏にかけては若い個体や幼虫が見られ、成虫は秋にかけて多く見られるようになります。秋になると特定の樹木に集まって交尾や産卵行動を行い、冬になると成虫のまま落ち葉の下や樹皮の隙間などで越冬します。
冬眠明けには再び活動を始め、次世代の産卵に備えます。年1化性で、世代交代のサイクルは比較的ゆるやかです。
観察ポイント

- 活動時期と時間帯:成虫は特に秋(9〜11月)に多く見られ、日中の暖かい時間帯に活発に動く。
- 生息環境:雑木林や里山の林縁部、森林公園、都市近郊の緑地など。特定の広葉樹がある場所で探しやすい。
- 観察のコツ:紅葉シーズンは体色が落ち葉に紛れやすいため、木の幹や樹皮に注意して観察するのがポイント。
- 越冬観察:冬場は落ち葉の下や朽木、樹皮の隙間などをめくると見つかることがあるが、無理に刺激しないよう注意。
類似種との違い
- ツヤアオカメムシとの違い:ツヤアオカメムシは鮮やかな緑色で、金属光沢がやや強い。体形もやや細身。エビイロカメムシは赤紫色で丸みを帯びた体形。
- クサギカメムシとの区別点:クサギカメムシは体色が褐色系で、光沢はなくより地味。また臭気が強く、農作物にも被害を与える害虫として知られる。
まとめ
エビイロカメムシは、カメムシ類の中でもその美しさと落ち着いた生態で知られる存在です。秋の森林で紅葉とともに見られる姿はとても風情があり、自然観察の楽しみを一層深めてくれます。地味で嫌われがちなカメムシですが、この種を通じてその奥深い世界に触れてみるのも面白いでしょう。
基本情報
- 和名:エビイロカメムシ
- 分類:カメムシ目 / カメムシ科
- 体長:12〜15mm
- 分布:本州、四国、九州
- 活動時期:5月〜11月(特に9〜11月に成虫多し)
- 生息環境:雑木林、里山、森林公園、街路樹周辺など
タグ(コンマ区切り)
エビイロカメムシ,日本昆虫研究所,エビイロカメムシの生態,エビイロカメムシの特徴,昆虫解説,昆虫観察,自然観察,昆虫図鑑,カメムシ観察,エビイロカメムシの見分け方










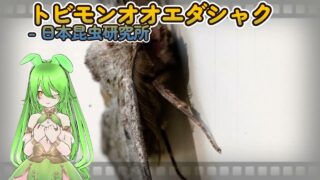










コメント