
##【日本昆虫研究所】ユノハマサラグモとは?落ち葉の下に潜むミクロの狩人を解説!
概要

ユノハマサラグモは、クモ目サラグモ科に属する体長数ミリほどの小型クモで、日本の森林や草地の落ち葉の下などに生息しています。精巧な「シート状の網」を張ることで知られ、身を潜めながら獲物を捕らえる戦略的な狩猟スタイルを持つのが大きな特徴です。極小の存在ながら生態系の中で重要な役割を担っており、知る人ぞ知る“ミクロの狩人”です。
特徴

ユノハマサラグモの体長は1.5〜2.5mmほどと極めて小さく、全体に淡褐色や灰褐色を帯びた保護色をしています。腹部にはうっすらと模様が入り、環境に溶け込む擬態的な外観を持ちます。体は柔らかく、脚は細長く繊細で、軽やかな動きと繊細な網作りに適した形態となっています。
視覚は弱く、主に獲物が網に触れたときの微細な振動を感知して反応します。そのため、行動や獲物への反応は非常に素早く、効率的です。
生態

ユノハマサラグモは地表近くに「シート状の網(水平網)」を張ります。この網は極めて薄く、地面と落ち葉の隙間に水平に広げられ、クモはその下側に待機し、上に落ちてきた小さな昆虫や節足動物を捕らえます。小さなアリ、トビムシ、ヨコエビなどが主な獲物です。
網は夜間に張られることが多く、昼間は巣の隅や落ち葉の下に身を潜めています。繁殖期には、雌が卵のうを持ち、体にくっつけて保護する行動が見られます。ふ化した幼体はしばらく母親の周囲にとどまり、やがて独立して自ら網を張るようになります。
観察ポイント

- 活動時期:4月〜10月が最も活発なシーズン
- 天候条件:湿度の高い日や雨上がりに網が見つけやすい
- 場所:落ち葉が積もった林床、苔むした地面、小枝の根元付近
- 時間帯:早朝や夕方、特に曇天の日は活動が盛ん
- 観察のコツ:双眼ルーペや虫眼鏡を用いて、落ち葉を静かにめくると網が現れることがあります
類似種との違い

- サラグモ類全体との違い:ユノハマサラグモは主に地表の隙間に網を張るが、他のサラグモ科には植物の上部や岩陰に巣を構える種も多い。
- コモリグモとの区別点:コモリグモは網を使わず歩き回って狩りをする一方、ユノハマサラグモは静的な網で待ち伏せ型の狩りを行う。
まとめ
ユノハマサラグモは、極小サイズながら緻密な構造の網を張り、戦略的に獲物を待ち受ける知的な狩人です。その生活は見過ごされがちですが、森の中での役割は小さくありません。目に見えないほどの存在にも、自然界の秩序を支える力があることを、このクモは私たちに教えてくれます。
基本情報
- 和名:ユノハマサラグモ
- 分類:クモ目 / サラグモ科
- 体長:1.5〜2.5mm
- 分布:本州、四国、九州
- 活動時期:4月〜10月
- 生息環境:落ち葉の下、苔の隙間、湿潤な森林の地表
タグ(コンマ区切り)
ユノハマサラグモ,日本昆虫研究所,サラグモ,極小グモ,昆虫解説,自然観察,昆虫図鑑,クモの生態,シート状の網,森林の昆虫





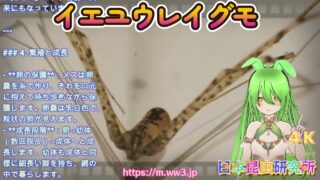















コメント